これまでにない画期的な書籍
ミッキーマウスの著作権が切れる前に延々と伸ばされる著作権保護期間、企業同士の特許訴訟合戦など、知財が如何に世の中にとって非効率であるかということを示す証拠はたくさんあるが、実際にそれらが必要のないものであることを、経済の観点から示した書籍というものは存在しなかった。本文では「知財は必要ない」証拠をたくさん挙げた論文であっても、結論では何故か理論が飛躍して「やっぱり特許は必要だから・・・」というような話でお茶を濁してしまうのが関の山だった。だが、本書はひと味もふた味も違う!本書のテーマはこうだ。知財は全て不必要悪。知財というものは独占のひとつの形態であり、それによって発明が増えることもなければ経済が発展することもない。
特に特許についての調査は秀逸だ。我々は小さい頃からエジソンやライト兄弟、ワットなどの偉人伝を聞かされて、特許は良いものだと刷り込まれているのだ。特許がなければ発明は起きないと信じこまされているのだ。だが、それらは皆嘘っぱちであり、本書が独占者によって塗り固められた嘘を全て暴いてくれる。事実はまったく逆であり、特許によって発明が増えることはないどころか、むしろ減ることの方が多い!というのだ。にわかには信じられないかも知れない。通説とは異なる事実なのだから、よほど理論的な思考が出来る人でなければ本書による主張を受け入れられないだろう。だが、人類はかつてそのような状況に直面してきたことを思い出して欲しい。ダーウィンの進化論しかり、コペルニクスの地動説しかり、これまでの通説を覆すような話は例え事実であってもなかなか受け入れられない。だが、皆さんにはぜひ本書を読んで目を覚まして欲しいのである!
本書では、先に挙げた著名な発明家たちが、如何に技術の発展に「寄与しなかったか」ということが赤裸々に綴られている。以下は蒸気機関を発明したことで知られている「ワット」についての記述である。
特許が保護されて生産が開始されると、ワットは競争相手である発明家たちの撃退にかなりの労力をつぎ込んだ。1782年にはさらに「クランク運動において、きわめて不当にも(マシュー・)ワズボローに出し抜かれた結果(中略)必要に迫られて」特許をとった。もっとも劇的だったのは、1790年代にもっとすぐれたホーンブロワーの蒸気機関の生産が開始されたときのことだった。ボールントンとワットは法制度を用いて全力で彼らを追い込みにかかった。
ワットの特許期間中に、イギリスでは蒸気機関の出力が一年あたり約750馬力ずつ増加した。これに対して、特許期間が終わってから30年間の出力の伸びは、一年あたり4000馬力以上だった。また、蒸気機関の燃料効率はワットの特許期間中はほとんど変わらなかったが、1810年から1835年までに、およそ5倍に増加したと推定される。
ワットの特許期間が終了すると、蒸気機関の生産性や効率が急上昇しただけでなく、蒸気動力も産業革命の原動力として真価を発揮した。30年間で蒸気機関車、蒸気船、蒸気紡績機など重要な重要なイノベーションが普及し、蒸気機関は改良された。
ちなみに、ワットは政治的な働きかけによって特許期間の延長にも成功している。お次はエジソン。
アメリカ映画業協会(MPAA)があまり宣伝していない事実だが、ハリウッド映画業界を築いたのは知的独占の締め付けを逃れた「海賊たち」だった。長く激しい競争を経て、1908年に映画や映画機材のおもな製作者たちーエジソンフィルム製造会社、バイオグラフ社などーが「モーションピクチャー・パテンツカンパニー(MPPC)」というカルテルを作った。そしてすべての映画製作者、配給者、映画館主にライセンス料を請求したのだ。そして使用料を払うのを渋った「独立系」映画製作者を精力的に告訴した。1909年にはMPPCの子会社であるゼネラルフィルムカンパニーが、無許可会社の用いる機材を没収して事業を妨害しようとした。
法定闘争と使用量の支払いを避けるための対応として、独立系映画製作者たちはニューヨークからカリフォルニアに拠点を移した。
カリフォルニアはエジソンの手が及ばないくらい離れていたため、フォックスやパラマウントといった映画製作会社は、カリフォルニアへ移って法を恐れることなくエジソンの発明に対して海賊行為をはたらいた。ハリウッドはたちまち成長し、連邦法はやがて西武にも及ぶようになった。だが(当時の)特許はまさに「限られた」独占状態を17年間認めてくれるだけだったため、充分な数の連邦保安官が登場する頃には、特許期間は終了していた。新たな産業が生まれたのは、エジソンの創造的財産を侵害したおかげでもある。
そしてライト兄弟。
独占力をまるで活かせなかったイノベーターとして突出した例が、ライト兄弟だ。飛行機の発展に対するかれらの貢献はむしろ控えめなものだったが、1906年には(かれらから見て)飛行機に似ているものすべてを対象とする特許の取得に成功したのだ。出願書類はもっと早くから書かれていた。つまり1903年3月から1906年5月まで、かれらは飛行機を組み立てたり他人にやり方を教えたり出来たのに、そうしなかったわけだ。特許が与えられてからも、かれらは飛行機の開発や発展促進や販売によって独占状態を活用しようとはせずに、むしろ秘密にしてさらに数年は見込み購入者に見せることを拒んだ。しかし自分たちの飛行機を売るためには一切努力しない一方で、ライト兄弟は法的措置にはとてつもない労力をつぎ込んでグレン・カーティスなど他人が飛行機を販売するのを阻止したのである。航空機の歴史に取っては幸運なことに、ライト兄弟の法的影響力はフランスでは皆無に等しかった。航空機の発展は、そのフランスで1907年頃に本格的に始められた。
輝かしい偉業を残した発明家たちが、実は特許を盾にとって科学技術、そして経済の発展を遅らせた張本人なのである。そういうと「そもそも発明家が居なかったら発明もなかった訳だから発展も何もないだろう」という意見が聞こえて来るかも知れない。だが、史実によればそのようなこともないことが分かる。
19世紀初めに、ジョージ・ケイリー卿はすでに、まともに飛ぶ飛行機の設計に必要な仕様書を書き留めて、詳述していた。かれのおもな問題点は、軽量動力源がないこと、飛行制御(特に方向と高度の変更)ができないことだった。オットー・リリエンタールは、自分が組み立てたハンググライダーで何度も飛行を成功させており、結果的に、飛行に重要なことをいくつも学んでいた。かれはハンググライダーに動力を取り付ける試験段階の初めに事故で命を落としている。実際のところ、「たわみ翼」のアイデアは、リリエンタールのおかげで生まれた。ライト兄弟が1902年に申請した最初の特許は、たわみ翼と方向舵を組み合わせて期待を操縦するシステムに対するものだったーつまり、既存の技術をほんのわずか改良したものである。
ライト兄弟の例は既存の技術まで自分たちの特許に取り込んでしまったという副作用まで示した悪どい例だが、それを指摘しすぎると論点がずれてしまうので話を戻そう。発明は、過去の偉大(だとされる)な発明家が発見しなくても、他の誰かによって発見されていた可能性が高い。何故か?その理由については次のように語られている。
これらーそしてその他の数十の物語ー微積分、クリッパー船、自転車、映画、MRI、自動車、ダクトテープーから得られる教訓は単純だ。最も偉大な発明は累積的で、同時発生する。最も偉大な発明は同時に、あるいはほぼ同時に、様々な発明家や企業からもたらされる可能性があり、製品はかれらの競争によって改良され、消費者にできるだけ低い価格で売られる。最も偉大な発明は、同時発生の産み出す社会的生産力が有効であればさらに迅速に広がり、さらに早く改良され得る。
発明家はたった一人で全ての知識を身につけたのだろうか?そんなはずがないのは誰もが分かることだろう。その時代の教育を受け、書物を読み、手に入る材料で実験を重ねて発明を行なったのだ。同じ時代に生きている人間であれば、同じような発想に至るのはごく自然なことだとは思わないだろうか?
特許がないとイノベーションが起こらない?
何故特許が無いほうが良いのか?全ての人が見落としているポイントは、特許は発明(出願)者による独占を認めるものだが、独占は自由経済にとって害悪以外の何者でもないということだ。独占は害悪。その当たり前のことが、「発明」という大義名分のために見落とされてしまっているのだ。そこで特許を肯定する意見としてよく見かけるのが、「特許によるインセンティブがあるから発明の量が増える」というものだ。なるほどたしかに発明が増えれば社会の役に立つので、特許という独占を許しても社会的にはそのメリットのほうが大きいと思える。だが、史実が示すのは全て逆の結果なのだ!特許は科学技術の発展、すなわち新たな発明の促進に繋がらないばかりか、むしろ発明の量を減らしてしまう要因になることが多い。本書では実に様々な実例をとり挙げて、如何に特許が役に立たなかったかということが示されている。以下はかつて特許が存在しなかったイタリアの医薬品業界における例だ。
いくつもの歴史研究や実証研究を見れば、イタリアの医薬品産業は1978年まで特に困っていたわけではないことは明らかだ。(中略)言い換えると、イタリアではまったく特許がなかったのに、一世紀以上にわたって医薬品産業が活況を呈していたわけだ。これが論点その一だ。論点その二は、特許が採用されてから30年の間、この産業の規模も、イノベーションの成果も、経済パフォーマンスも、目に見える形ではまったく改善していないということだ。手に入るどんな指標を見ても、イタリアの医薬品産業は特許の導入により助かるどころか被害を被っていることがわかるし、この問題を検討した専門家はすべて、これとまったく同じ結論に達している。
医薬品といえば「開発に莫大なコストがかかるので特許が必要」と声高らかに謳われている業界である。その医薬品業界ですら特許などなくても業界が発展するということが、史実によって証明されている。逆に、特許を導入したことによって発明が、イノベーションが加速した業界というのは存在しないのだ。
本書では「特許を導入した国で、導入後に発明が増えたという事例はない」と結論付けられている。発明が増えないのに何故特許という制度が必要なのだろうか?否、社会にとっては一切必要ない制度なのである!
むしろ逆に、特許のないところではイノベーションが加速して製品の品質は向上し、経済が発展する。当然だ。しっかりと競争原理がはたらく市場は発展するのである。
特許が独占のためにある
ここで少し視点を変えて、特許を活用してビジネスをしている人が書いた書籍を紹介したい。こちらの書籍は、確固たる特許戦略を持っているキヤノンのサクセスストーリーを描いたものである。著者はキヤノンの特許部隊を率いていた丸島氏。かつてプリンタ技術において600もの特許をとり、自社技術をガチガチに固めて独占状態を築いていた怨敵ゼロックスに戦いを挑んで勝利したというもので、キヤノンはゼロックスの特許に一切抵触しない新技術を使ったプリンタを開発し、しかもそのプリンタ技術がゼロックスの技術より効率が良くどんどんシェアを伸ばして言ったため、最終的にゼロックスからクロスライセンス契約の申し出を受けたというのがストーリーの概要である。その丸山氏によれば、強い特許戦略とは次のようなものである。
しかし私は、企業における特許は商品ではないと考えています。もちろん商品のように扱える側面はあります。しかし特許を商品として活用するのは、企業としては主たる問題ではなく、従とすべきです。基本は商品ではなく、やはり権利として考えて活用するべきだと思うのです。
つまり企業活動における特許は、自分の事業を守るために独占的に使うのが本道であるはずです。排他独占的に、誰にも真似させない、ライセンスも出さない、それが一番いい活用の仕方なのです。そうすればその事業は独占できるわけですから。この考え方がバックボーンにある会社の特許戦略は、絶対に強いのです。
筆者も氏の意見には同意である。現状の特許制度下においては、特許は独占のために使うのが特許の保護を受ける側にとって一番である。そもそもそのための仕組みであるから。
だが待って欲しい。キヤノンがプリンタ事業に乗り出そうとしたとき、そこに特許がなければ、ゼロックスが膨大な特許で独占状態を築いていなかったらどうだっただろうか?
丸山氏は特許戦略の落としどころとしてクロスライセンス契約(を有利な条件で結ぶこと)を挙げているが、その点については次のように述べている。
伝え聞くところでは他の事務機メーカーの多くが、個別にライセンス料を払っているそうです。そうであるならば、このクロスライセンスが価格競争上キヤノンにもたらした恩恵は大変大きなものになるわけです。またこれも数字には表れないことですが、自由に特許が使えるとなると設計の自由度が高まります。よりよい製品の開発にも、このクロスライセンスは重要な恩恵を与えたのです。
当然ながら、特許という制度がないほうが製品の自由度が高まるということは疑いの余地はない。となれば、特許を取得したり、クロスライセンスを締結したりといった一連の手間は、単なるコストでしかなかったとは考えられないだろうか。特許がなければ「ゼロックスの特許を回避する努力」というものは無かっただろうが、その代わり、製品をたくさん売るために品質を改良する努力は怠らなかったはずである。巨大帝国に挑んだキヤノンの特許部隊の努力は大変なものであろう。だが、特許という仕組みそのものがなければ、もっと違うところに力を注げたはずである。
あと、ついでに指摘しておくが、プリンタというひとつの製品で600もの特許が取得されているという状況は明らかに異常だ。つまらないアイデアに対して特許を与えられている現状は、特許制度が破綻している証拠であるとしか言いようがない。
独占のない業界は発展する
独占が働く経済は衰退するが、逆に独占がない市場は発展するし、イノベーションが盛んに行われる。今、IT業界で最もイノベーティブな活動が行われているのはウェブ業界だという意見に異論を挟む人は少ないだろう。FacebookやTwitterは絶好調だし、ソーシャルゲームを提供する会社はどこも賑わっている。Google帝国だって揺らぎそうもない。日本でもDeNAやGREEには一流の人材がどんどん集まっていく。今まさに、ウェブ業界はIT業界における花形であると言っても過言ではないだろう。なぜウェブ業界はかくも成功しているのだろうか。それは、特許侵害で訴えられるリスクが少ないからだと思う。かつてアマゾンが主張した「ワンクリック」のような特許は確かに存在するが、ウェブサイトをターゲットとした特許訴訟を起こすのは難しいのである。なぜなら、サーバー側でどのようなことが行われているかは外から分からないので、サーバー側のことでは訴えようがないのである。(Javascriptは新たに特許訴訟の対象になる可能性を孕んでいるが。)
今やDeNAとGREEは熾烈な戦いを繰り広げているが、競争が起きるのはとても良いことである。もし仮にソーシャルゲームの仕組みに対して特許が取得されてしまっていたらどうだっただろう。当然、ソーシャルゲームの特許を取得しなかった企業は廃業に追い込まれることになる。そのような状況にはならず、お互い切磋琢磨することを強いられる環境であるからこそ、サービスの向上に勤め、躍進したのである。「釣りゲーム」にも特許を取得しなかったから切磋琢磨で発展しているのである。
ところで、ウェブ業界で「特許」と聞いて思い出さずにいられないのがGIF特許問題である。特許によってGIFファイルフォーマットの画像が使えなくなる可能性があったため、多くのサイトでGIFファイルが不採用になったり、GIFファイルを扱う無料ソフトが姿を消したり、まさに大混乱であった。特許は非常に影響範囲が広く、しかも独占によって多くの開発者を萎縮させてしまうことになるのである。
アイデアのコピーにはコストがかかる
少し話が横道に逸れたので、話を書評に戻そう。特許を肯定する意見で多く見られることのひとつに「苦労して発明したものをタダでコピーさせてしまったら発明する意味がなくなるじゃないか」というものがある。だが、それは大きな誤りだと、本書では指摘されている。アイデアをコピーする=真似るのはタダではないのだ!
ひとたび発見されたアイデアは誰でもフリーに模倣できるという見解は曼しているが、事実とかけ離れている。アイデアが費用なしで獲得できる例もたまにあるがー概してアイデアは伝達が困難で、伝達するリソースには限界がある。経済学者は大学教授を兼任して、古いアイデアを教えて(伝達するのが容易でも安価でもないので)かなりの稼ぎを手にしている人も多いが、そういう人の一部が研究論文ではこれを否定しているのは皮肉な話だ。ほとんどの場合、模倣には努力が必要であり、さらに重要なことには、もとのイノベーターから製品もしくは教育サービスを購入する必要がある。つまり、ほとんどのスピルオーバーには価格が付いているのだ。これは当たり前のことである。アイデアを理解するには専門性や知識が必要だし、さらにそのアイデアを学習して自分が利用するまでには、かなりの努力が必要なのだ。つまり、特許などなくても発明者には充分なメリットがあるということだ。
そもそも、これほどインターネットが発達してアイデアが公開されているにも関わらず、実際にはアイデアが伝達されるまでにはかなりの時間を要する、または伝達されない場合もある。イタリア出身の著者は「イタリア以外の国では美味しいエスプレッソが飲めない」と嘆いているが、エスプレッソのレシピは公開されているものの、美味しい淹れ方というのはまるで伝達していないというのである。先日、在日アメリカ人が「日本にはパン屋がない」と嘆く動画がYouTubeに投稿されて話題になった。アイデアが公開されているのに伝達しないなんておかしい!と思うかも知れない。だが、実際にはそのような例はゴマンとある。人類の食生活を画期的に改善した「農業」ですら、伝搬する速度はかなり遅かったそうである。
特許による制約がない世界というのは、実は技術者にとっては労働条件が改善されるチャンスである。特許がなければ技術者こそが全てだ。ライバルのアイデアを真似するには高い技術を持った技術者が必要だし、そもそも技術者を引き抜かれるとそのアイデアを失う(学習しなおす羽目になる)ばかりか、ライバルの手にスキルまでもが渡ってしまうことになるので、経営者には高い給料で技術者を引きとめようとするインセンティブが働くことになる。その証拠に、凌ぎを削っているDeNAとGREEによるエンジニア争奪戦は凄まじい。入社準備金制度なるものまで出てくる始末である。Googleはいきなり全社員に対して10パーセントの昇給と、1000ドルのボーナスを至急したということがニュースになった。何とも羨ましい話であるが、このように競争が働いている市場では、技術者は労働条件が改善されることになる。
一方、特許でガチガチに守られた業界では事情が異なってくる。以下は医薬品業界に関する記述の引用である。
医薬品の停滞に関するもっともよい説明は、マーケティング偏重になったというものだ。特にFDAが5年前に、企業が直接消費者を標的にすることを認めて以来その傾向が強い。ボストン大学公共保険学部のアラン・セーガー教授によると、特許役を作る企業での研究開発従業員の数は、1995年から2000年の間にちょっと減っているのに、マーケティングの従業員数は59パーセントも増えている。「製薬会社は画期的な研究の価値をもてはやすが、実際に使っているリソースは、プレスリリースが示唆するよりもはるかに少ないようです」とセーガーは語る。
特許があることで得をするのは、技術者よりもマーケッターなのである。そしてライセンスの契約や訴訟を担当する弁護士や、独占で大儲けをするごく一部の企業の株主なのである。全体で見れば1パーセントもそのような恩恵にはあずかることが出来ないだろう。
著作権について
本書では、特許だけでなく著作権すらも不要であり、著作権がなくても大金持ちになることは出来ないが、充分に儲かるビジネスがあるという事例が示されている。フリー(自由な)ソフトウェア、すなわちコピーレフト支持者である俺にとっては、著作権なんざクソックラエであり、本書の意見に賛成だ。大事なのでもう一度言うが、著作権なんざクソックラエだ!ソフトウェア業界におけるイノベーションと著作権の問題を論じるにあたり、本書ではオープンソースソフトウェアとGPLが取り上げられている。ソフトウェアのパートはかなり気合の入った解説がなされており、IT業界に身をおく者であれば一見の価値アリである。
ツケを払うのは誰か
特許による独占を許すことによって、結果的に損をするのはライバル企業でもなければ技術者でもない。国民そのものなのである。競争がなければサービスや製品の品質は向上しないし、価格が下がることはない。さらに本書では次のように指摘する。ほとんどの人は、利益を得る確実な方法というのは「安く買って高く売る」ことだと学んだ。(中略)重商主義の罠と悲劇は、この個別には正しい哲学が、国家政策に変換されたときに生じる。(中略)この重商主義の現代版を吹聴する者たちの頭の中では、WTOというのはなるべく自由貿易を推奨すべきだ、なぜかといえばわれわれが「連中の」製品を安く買えるから、というものになっている。同時にWTOは「知的財産」はできるだけ保護して「われわれの」映画やソフトや医薬品を高値で売れるようにすべきだ、ということになる。この愚論が見落としているのは、いまも三世紀ほど前と同じく、「連中の」食料を安く買うのはよいことだったが、「連中が」映画や医薬品を高値で買うということは、「われわれ」のほうもやはりそれを高値で買わされるということだ。実は医薬品やDVDの例が証明しているように、独占者は「連中」よりも「われわれ」に対し、もっと高値で売りつける。
つまり一番のツケは独占を許してしまっている国民、とりわけ独占する側にない数多くの国民によって支払われるのである。何という悲劇だろうか!!
特許法を含めた法律は、すべて国民全員のために存在するべきなのである。一部の独占者たちだけに都合の良い法律は間違っている。だからといって、今日から「はいそうですか」と法律が変わるわけもないし、医薬品やDVDの値段が下がるわけでもない。だが、独占者はいつの時代も手前勝手な理論武装を身をまとい、我々を欺くことに長けている。本書によってぜひその一端を垣間見て頂きたい。






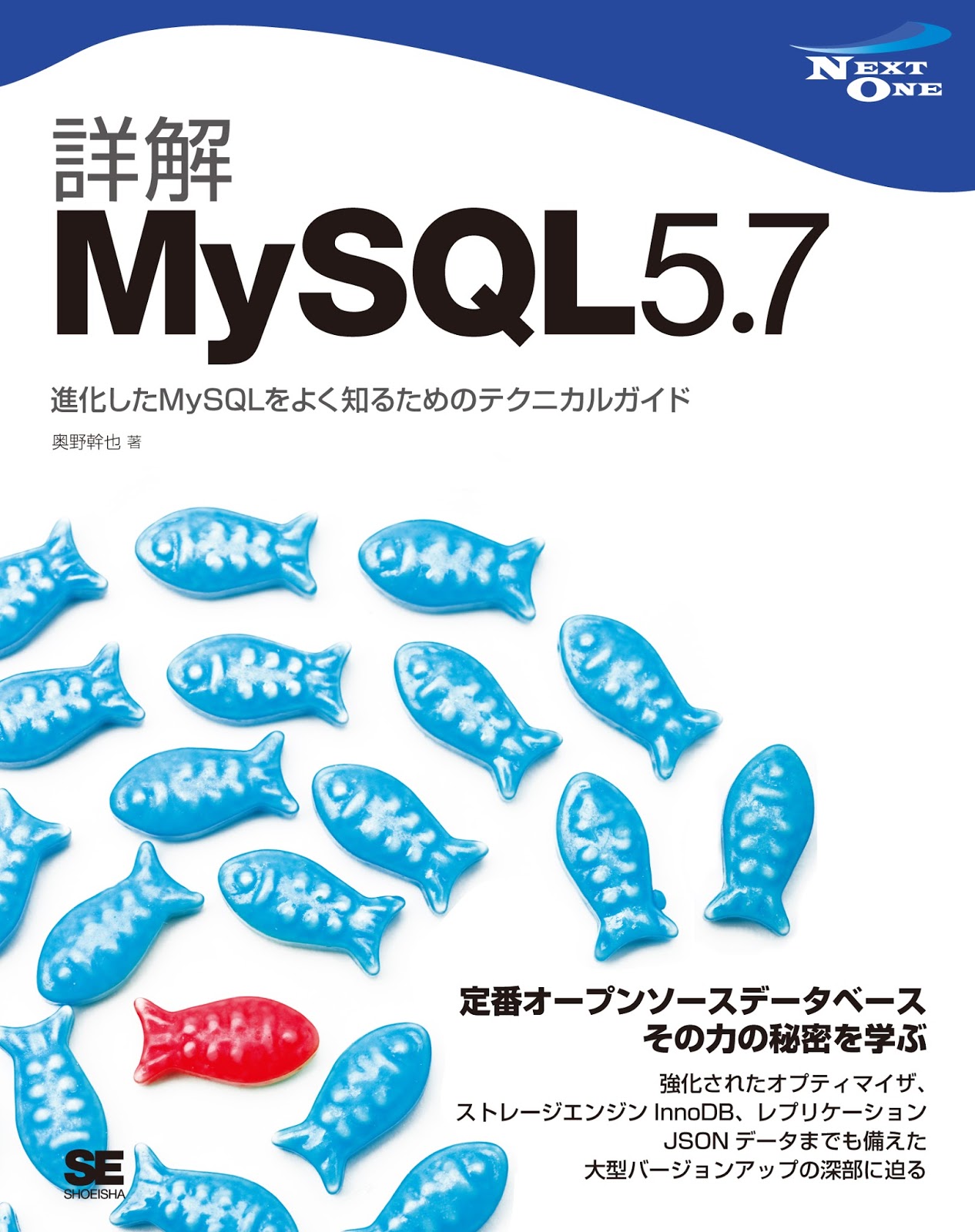



0 コメント:
コメントを投稿